機械工学系
2015年7月24日
機械工学系 熊谷一郎准教授が可視化情報学会で学会賞(技術賞)を受賞しました
総合理工学科機械工学系 熊谷一郎准教授が第26期可視化情報学会で学会賞(技術賞)を受賞しました。
表題:Story Visualization of Novels with Multi-Theme Keyword Density Analysis
著者:
山田美幸(日本大学 英語講師)(明星大学 客員研究員)
村井祐一(北海道大学 工学研究院 教授)
熊谷一郎(明星大学 理工学部 准教授)
シェイクスピア劇における登場人物の相関関係の可視化をテーマとした論文が高く評価されました。
2015年7月17日
8月開催のオープンキャンパスでは『夏の特別講義』を開講します!
オープンキャンパスシーズンも本格的になりましたがいかがお過ごしですか。
理工学部 総合理工学科では、8月開催のオープンキャンパスで『夏の特別講義』を開講いたします。
総合理工学科の各学系で学ぶことが社会とどのように関係しているのかを知る良い機会となるでしょう。
是非『自分の学びたいものがどこにあるのか?』を探求する夏にしてください。
皆さんの参加をお待ちしております!
【8月オープンキャンパスの開催日】
8月1日(土) ・ 2日(日) ・ 23日(日)
【開講テーマの詳細はコチラ→】総合理工学科『夏の特別講義』テーマ一覧
2015年7月9日
機械工学系 緒方准教授率いるチームが第3回カーレット大学選手権で優勝しました
平成27年7月5日(日)、東京農工大学で行われた「第3回カーレット大学選手権」に
機械工学系 緒方正幸准教授と機械工学専攻院生2名・機械工学系学生2名が出場し、見事優勝いたしました。
カーレットは氷上ではなく卓上で行うカーリングで、頭脳スポーツとも呼ばれています。
フェアプレー精神が重んじられ裁定はお互いのチームで行います。
世代を問わずゲームを楽しみながらコミュニケーションを深められるということで
注目が集まっています。



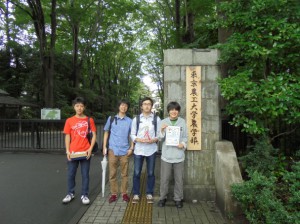
2015年6月25日
環境・生態学系 田中修三教授に東京都から感謝状が贈呈されました
理工学部総合理工学科 環境・生態学系 田中修三教授に、東京都から環境行政への貢献に対する感謝状を贈呈されました。
田中教授は、東京都の「環境影響評価審議会」において水質汚濁と土壌汚染の専門家として、
環境影響評価に対する意見提出や都担当者への助言を行い、
さらに東京都環境影響評価技術指針の策定にも関わってきました。
その貢献に対し、東京都知事より感謝状を贈呈されました。
◆環境影響評価審議会・・・東京都内の建設・開発事業に関して、事前に当該事業が環境に及ぼす影響を評価するための機関
2015年6月20日
総合理工学科 電気電子工学系 石田 隆張教授の寄稿がキャパシタフォーラム会報に掲載されました
本学理工学部 総合理工学科 電気電子工学系 石田 隆張教授による寄稿が、キャパシタフォーラム会報(2015年 通巻10号)に掲載されました。
◆ 寄稿タイトル:『EV急速充電時のログデータを用いたリチウムイオン電池の劣化分析』
※ キャパシタフォーラムとは、エネルギーキャパシタシステムの技術開発および利用、その他電気エネルギーの効率的活用に関する調査、情報の収集、提供、普及そして啓蒙活動のための企画立案および推進を行う団体です(※同団体HPより文言を部分引用。URL:http://capacitors-forum.org/jp/)。
2015年6月15日
建築学系 齊藤研究室が総合資格学院Architekton+で紹介されました
建築学系 齊藤哲也先生の研究室の取り組みが、
総合資格学院のフリーペーパー「Architekton Plus(+)」6月号で紹介されました。
2013年度の卒業論文・卒業設計の実例や、
学生自らが制作物を構想し設計と施工までを一貫して行う体験学習「セルフビルドワークショップ」の取り組みが
掲載されています。
2015年5月8日
環境・生態学系 木下 瑞夫教授所属の長期専門家グループが(公財)日本都市計画学会学会賞(石川賞)を受賞することが決定しました
環境・生態学系 木下 瑞夫教授所属の都市開発技術支援プロジェクト『JICA長期専門家グループ』が、
公益社団法人 日本都市計画学会における学会賞(石川賞)を、後述の関連官公庁・団体と共に受賞することになりました。
石川賞は、都市計画に関する独創的または啓発的な業績により、
都市計画の進歩、発展に顕著な貢献をした個人または団体を対象に授与される賞で、
この度は、『タイ王国への土地区画整理技術移転とその自立的発展』という作品名のもと、
国土交通省都市局、独立行政法人国際協力機構、タイ王国内務省公共事業・都市計画局、及び、バンコク首都圏庁と共に同賞が授与されることとなりました。
2015年5月7日
研究科長から大学院生へメッセージ
「明星大学大学院で学ぶことの意義」
現在、大学で学んでいる皆さんの中には、日頃の学習や実験、演習に触発されて、
「自分が関心を持つ課題についてもっと深く研究したい」、「もう少し時間をかけると新しいものを創り出すことができる」と思っているひとも多いことと思います。
研究や創造は社会に出てからもできますが、研究や創造の方向性を指し示す人がいてくれたら、それらはさらにすぐれたものになるでしょう。
大学院は、そのような発見や創造のための研究を進めるための方向性を指し示す場です。
関連分野の先生たちから研究を深化・発展させるための知識と考え方を学び、研究室の先生と研究内容について議論発見や創造に取り組んでいくということは、
苦しいけれど楽しいことだとは思いませんか。
明星大学理工学研究科では皆さんにそのような場を提供します。
明星学苑の教育方針の一つに「手塩にかける教育」があります。
これは、明星大学理工学研究科においても生かされています。
理工学研究科の教員は、研究に不慣れな学生の皆さんに対して研究の進展に合わせた指導を行います。
研究は楽しいものです。研究室の先生や仲間たちと一緒になって研究に取り組みませんか。
苦しかったけれど楽しい研究生活であったと思える日がきっとくることでしょう。
大学院で学ぶことの良さに、ものごとを論理的にかつ客観的に見つめることができるようになることがあげられます。
発見や創造したものを発表する時にこのようなことを問われるからです。
論理性や客観性は、社会に出たときにもっとも必要とされる素養です。
社会はこのような素養を身につけた人を求めているのです。理工学研究科でそのような素養を身につけてください。
社会人の皆様にご案内いたします。日頃の仕事を通じて「もう少し考えをまとめたい」、「研究能力を高めて日頃の仕事に生かしたい」とお考えであれば、
大学院で学ぶことも一つの方法です。
研究とそのための勉強を続け、結果として高みから仕事や自分自身を見つめてみる機会を得ることによって幾層倍の充実感を得ることができるでしょう。
明星大学理工学研究科は、そのような皆さんを支援します。「手塩にかける教育」の必要性は社会人の皆様にも通じること考えます。
平成27年4月
理工学研究科長 木下 瑞夫
2015年5月7日
学部長から新入生へのメッセージ
新入生の皆さん、入学おめでとうございます。
今年度、理工学部は440名の入学者を迎え、我々教職員は新たな気持ちで4月からスタートしました。
皆さんは、大学生活にいろいろな思いを抱き、入学されたことと思います。
4年間の過ごし方は人によってさまざまでしょうが、皆さんのこれからの人生に大きな影響を与えることは間違いありません。
皆さんには、大学4年間でいろいろなことを学び、「知性」、「感性」、「理性」をさらに養ってほしいと思います。
「知性」は、物事を知り、考え、判断する能力です。大学での講義・実験実習で学ぶことの多くは、知性を養うことにつながります。
哲学者フランシス・ベーコンの格言にありますように、「知は力なり」です。
また、私の好きな言葉のひとつに、中学以来の旧友から聞いた、「知識は人を自由にする」があります。
この言葉の意味は、私個人的には、さまざまな知識や考え方を身につけることによって選択肢が増える(自由度が増す)ことであると考えています。
例えば、我々、理工学部教員は、卒研生や大学院生とともに、それぞれの専門分野でオリジナリティーのある、創造的な研究を目指して活動していますが、
既存の知識の新たな組み合わせで、誰も気が付かなかった研究成果が生まれることは少なくありません。
すなわち、習得した知識が増えるほど、その組み合わせに基づいた発想の選択肢が多くなり、未解決の問題へのアプローチや新技術・方法論の開発へとつなげることができます。
一方、「感性」と「理性」は、あなたの周りの人とのコミュニケーションを通して培われる面が大きいと思います。
「感性」は感受性と捉えられますが、単なる受動的な感受性ではなく、周りの環境の変化に対応でき、能動的で創造的な能力をも含んでいるという意味もあります。
「理性」も調べてみると意味深い言葉ですが、シンプルには、感情におぼれず、筋道を立てて物事を考え判断する能力と思います。
自らの感情や欲求を抑え、周囲の人との協調をはかったうえで行動することは、人生のいろいろな場面でしばしば重要となります。
大学生活において、同級生、先輩、後輩、教職員などいろいろな人との交流やいろいろなことの体験を通して、「感性」と「理性」を養って行ってほしいと思います。
先ずは、皆さんには、今、興味を抱いていることやチャレンジしたいと思っていることに、積極的にかつ主体的に取り組んでほしいと思います。
そして、得られる「知性」と「感性」を組み合わせて、「理性」をもって物事に対処する能力を高め、自らの人生の可能性をどんどん引き出してください。
卒業のときに進化した皆さんの姿を見ることを楽しみにしています。
平成27年4月
理工学部長 清水 光弘
2015年2月28日
スマートコミュニティ実証事業におけるシンポジウムに電気電子工学系 伊庭教授がパネリストとして参加しました
2月18日(水)、沖縄県宮古島市で行われたスマートコミュニティの実証事業におけるシンポジウム
「~島しょ型スマートコミュニティの可能性~」に電気電子工学系 伊庭健二教授がパネリストとして参加いたしました。
宮古島市は島内でエネルギーの見える化など、インフラ、情報通信、電力やエネルギーなどを有効的に活用しようという
次世代の街づくりを実施しており、その取り組みについて他のパネリストと意見を交わしました。
詳しくはこちらをご覧ください。
宮古新報(2月19日発行)には伊庭教授のコメントも掲載されています。